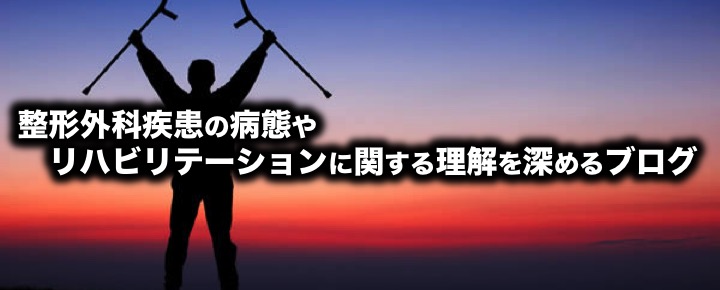リハビリって一回いくら?料金や時間はどうなっているの?

リハビリテーション(以下:リハビリ)を受ける場所として
まず最初に思い浮かべるのは病院でしょう。
事実、怪我や運動機能の低下によって、
入院や外来にてリハビリテーションを受けることが多いと思います。
では、皆さんは、リハビリとはどのくらいの時間行い、
どのくらいの料金が生じるかご存知でしょうか?
今回は、主に整形外科疾患におけるリハビリの時間や料金について解説します。
※ここでいうリハビリとは、接骨院やマッサージなどではなく、医師の指示のもと行う理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが行うものを指します。
リハビリの時間はどのくらい?
リハビリにかかる時間は基本的に1単位20分という単位で計算します。
1単位=20分
2単位=40分
3単位=60分
といったように20分刻みである事がほとんどです。
(一部、地域包括ケア病棟などそのくくりがない場合もあります)
実際に何単位行うかは、医師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの療法士の提案のもと決まります。
体力的な限界もありますし、入院の場合でも回復期病棟・急性期病棟・地域包括ケア病棟、もしくは外来リハビリなどによっても上限や制約が変わってくるので無限に行えるわけではありません。
そのあたりは、「通常リハビリは何単位行うか」などを確認するのも良いかと思います。
この1単位20分を基準として一回の料金も決まってくるのです。
リハビリの料金はどのくらいかかる?
では、実際にリハビリの料金はいくらになるのでしょうか?
先に述べたように、1単位の単価が決まっています。
そして、これは厚生労働省が診療報酬として定めている決まりがあり、
病院ごとに異なるものではありません。
(数年に一度改定があり、その都度)
また、疾患の区分によっても異なり、
・脳血管疾患
・運動器
・廃用症候群
・心大血管
・呼吸器
と病名によって区分けされています。
今回は、主に整形外科疾患が区分される運動器について解説します。
まず、以下の表をご覧ください!
(令和2年度診療報酬改訂時のものであり、当記事作成時の最新の情報)

(PT-OT-ST.NETより引用)
※1 月に13単位を限度に入院中の要介護被保険者に対して標準算定日数を超えてリハビリを行う場合
※2 標準算定日数の1/3を経過したのちに要介護被保険者に対し過去3ヶ月以内に目標設定支援・管理料を算定していない場合は、所定の点数の90/100に相当する点数を算定する
表の赤枠で囲った部分が運動器の点数表になります。
点数というのは、1点=10円となります。
つまり、点数×10=料金となります。
例えば、100点という点数の場合100×10=1000円となります。
また、縦軸には施設基準というものがあります。
各施設によって人員配置や設備などによっていずれかの区分に該当します。
この区分も各施設に確認すると良いでしょう。
さて、いよいよ実際の料金を考えてみます。
施設基準Ⅰを満たす病院で、骨折などの怪我によって運動器疾患におけるリハビリを40分受ける場合は一体いくらになるでしょう?
まず施設基準Ⅰの運動器では、1単位20分で185点となります。
40分の場合は185点×2となりますので370点になりますね。
また、1点が10円になりますので、370点×10で3700円ということになります。
実際には、この値段に対して医療保険が適応となりますので、
3割負担の場合は、1110円
1割負担の場合は、370円
となります。
これがおおよその値段になります。
行った時間と疾患の区分、施設基準によって料金が異なります。
さらに、注釈にあるように疾患を罹患した日からの算定日数の上限を超えた場合などによっても若干料金が異なってくるのです。
(実際には、さらにリハビリテーション実施計画書や各種検査を実施した場合に、加算が追加されていることもあります)
まとめ
今回は、主に整形外科疾患におけるリハビリの時間や料金について解説しました。
さて、皆さんは一回あたりのリハビリの料金が高いと感じましたか?
低いと感じましたか?
日本は医療保険が適応されるので額面上はかなり安い金額に見えますよね。
これからは病院でもらった明細などにも目を通してみるのも面白いのではないでしょうか。
スポンサーリンク

 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる