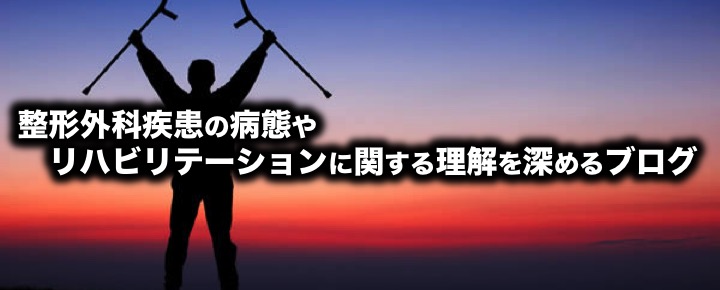変形性膝関節症の手術に伴うリスクは?感染や血栓に注意!

変形性膝関節症は、高齢社会を迎えている日本にとって増加の一途をたどっていると言われています。
症状が重度の場合、【手術療法】を行う場合が多いです。
手術を行うことで除痛効果が得られ、再び歩行を行えるようになることが最大の利点です。
しかしながら、どんな手術にも必ずリスクは伴います!
変形性膝関節症は、日本において潜在患者を含めると3,000万人が有するとも言われる退行性疾患です。
症状が重度となると、手術療法が選択される場合が多いです。
人工膝関節全置換術は変形性膝関節の治療法の中では最も代表的な手術手技です。
変形性膝関節症の手術に関する詳しい記事はこちら
→変形性膝関節症の手術療法「TKA」とは?他にも手術の種類があるの?
手術療法によって得られる効果は、除痛や変形の矯正が挙げられ、これらの影響によって再び歩行を獲得することが出来ます。
しかしながら、手術療法が必ずしも安全で万能というわけではありません。
手術というからには少なからずリスクを伴います。
人工膝関節全置換術におけるリスク、またはデメリットとして挙げられるのは、
・再置換
・関節可動域の低下
・血栓症
・感染
などです。
中には命に関わるようなリスクもあるため注意や事前の覚悟が必要といえるでしょう。
そこで今回は、これらの変形性膝関節症の手術に伴うリスクについて一つづつ解説していきます。
変形性膝関節症に関する詳しい記事はこちら
→変形性膝関節症(膝OA)とは?治る疾患なの?リハビリテーションの内容は?
→変形性膝関節症におけるリハビリテーションの評価項目とは?
再置換のリスク
人工膝関節に置換した後から常に抱えているリスクがこれです。
いわゆる人工関節自体の耐用年数が問題となるのです。
人工関節を構成しているポリエチレンの磨耗などが主体となって緩みが生じるのです。
一般的に、その耐用年数は20年と言われていますが、これは活動量や動作パターンなどにも影響を受け、一概に言えることではありません。
また、転倒や骨折によっても、破損や緩みを生じることがあります。
これらの場合は、「再置換」となり、再び手術を受けなければならないのです。
関節可動域低下のリスク
変形性膝関節症は、関節の変形などから、関節可動域の低下をきたすことが少なくありません。
そのため、人工関節への置換によって、変形を矯正することで関節可動域が増大する例は多数見られます。
しかしながら反対に、関節可動域は十分要しているが、疼痛が重度のため、手術に踏み切った人も中にはいるのです。
その場合、インプラントの種類にもよりますが、おおよそ獲得可動域は屈曲で120°前後と言われています。
→全人工膝関節置換術(TKA)のインプラントの種類は?PS型とCR型の違いは?
そのため、もともと出来ていた正座は出来なくなったり、術後の状態やリハビリテーションの進行具合によっては、関節可動域が低下することも珍しくありません。
その場合は、リハビリテーションに力を入れて取り組んでいくしかないのです。
変形性膝関節症に対するリハビリテーションの記事はこちら
→【変形性膝関節症】TKA術後のリハビリテーションって何をするの?
→変形性膝関節症に対する筋力トレーニングとは?自宅で出来る方法は?
血栓症のリスク
膝関節の手術に限ったことではないですが、下肢の手術後に生じやすい合併症が「血栓症」です。
正式には、「深部静脈血栓症(DVT)」と呼ばれ、通称「エコノミークラス症候群」などとも言われています。
深部静脈血栓症は、下肢の静脈血がうっ滞し、血管内に血栓ができることを言います。
これだけなら良いのですが、血管内に出来た血栓は、血管の中を流れて肺に達し、「肺塞栓症」と呼ばれる命に関わる重篤な合併症を招くため、大変注意が必要です。
予防方法は、術後より足首や足趾の運動を行うことや、血栓予防のための靴下を履くことです。
感染症のリスク
感染症も膝関節特有のものではありませんが、手術後には必ずつきまとうリスクです。
手術時に患部から細菌が入り込む場合と、手術後数年経った時でも何らかの感染症にかかることによって、細菌が患部に発生する場合とがあります。
感染は一度生じると、激しい痛みや、腫脹、発熱などの症状を伴います。
状態にもよると思いますが、基本的には再置換を余儀なくされます。
適切な予防が行えるかというと難しく、術後早期は清潔にし、入浴は避けるなどの対応をするしかないですね。
→下肢の手術後に注意すべき血液データは?CRPやDダイマーの持つ意味は?
まとめ
今回は、変形性膝関節症の手術に伴うリスクについて解説しました。
手術を受ける側だからと受け身にならず、正しい知識を持って手術に臨みましょう。
また、これらのリスクやデメリットも考慮しながら、手術を行うか否かを整形外科医など専門家と協議すると良いと思います。
スポンサーリンク

 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる